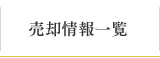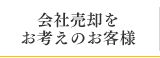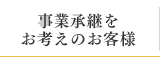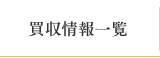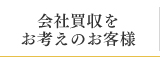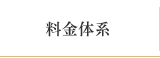1、M&A会計の変遷

長い間、わが国ではM&A会計の拠り所となる統一された会計基準が存在せず、実務上は既存の会計基準や旧商法などを部分的に用いて処理を行っていました。
そのため、同じようなケースでも全く異なる会計処理が採用されることもありましたが、平成15年10月には「企業結合に係る会計基準」が制定され、合併・株式交換・株式移転などが行われた場合の会計処理についての規定ができ平成18年4月以降に開始する事業年度から適用となりました。

上記以外に、企業結合会計基準と事業分離等に関する会計基準とともに、より詳細なルールを規定した指針「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」も公表されています。
さらに、わが国における企業結合の活発化に伴い、平成20年12月に企業結合会計基準が改正されました。その結果、持分プーリング法の廃止が決定、負ののれんの会計処理、株式を取得対価とする場合の当該対価の時価の測定日などが変更されました(これに伴い、「連結財務諸表に関する会計基準」なども改正されています)。
平成25年9月には「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」が改正されました。その結果、少数株主持分(非支配株主持分)の取扱い、企業結合に係る取得関連費用の会計処理、暫定的な会計処理の確定に関する処理が変更されました。
2、M&Aの各手法と会計処理
代表的なM&A手法の会計処理です。
各手法の会計処理は、平成20年12月改正の企業結合会計基準に基づいています。
合併
合併の際は、企業結合会計基準に従い、パーチェス法により会計処理を行います。
パーチェス法では、取得企業は、資産や負債の取得原価および対価として交付する現金や株式を、すべて時価に基づき計算します。
その際、受け入れた純資産(時価評価した資産と負債の差額)と対価との間に差額が生じる場合には、「のれん(または負ののれん)」を計上します。
会社分割
会社分割では、分離元企業は事業分離等会計基準に基づき会計処理を行い、分離先企業(受入企業)は企業結合会計基準に従った会計処理を行います。
分離元企業の会計処理は、移転した事業に関する「投資が清算されたか、継続しているか」により異なり、この違いによって、個別財務諸表上で移転損益を認識するかどうかが決定されます。
清算と継続の判断基準は、具体的には分離先企業から受け入れる対価の種類によって判定します(対価の種類としては、現金等のみ、分離先企業の株式のみ、現金等と分離先の株式の両方、という3つのケースがあります)。
分離先企業においては、合併とおおむね似たような会計処理が行われます。
株式交換
株式交換においては、完全子会社となる会社が完全親会社となる会社に発行済株式の全部を取得させます。
そして、その対価として、完全親会社の株式等が完全親会社から完全子会社となる会社の株主に交付されます。
完全親会社の会計処理はパーチェス法が適用され、子会社株式を株式交換日における完全親会社の株価で計上します。
完全親会社の資本の額は、交付した株式の分だけ払込資本を増加させます。
完全子会社側では、単に株主が変わるだけですので原則として会計処理は発生しませんが、新株予約権や新株予約権付社債などを発行している場合などには、消滅に関する処理が必要になります。
株式移転
株式移転は既存の会社が完全子会社となるために、新たに完全親会社を設立する手法ですが、基本的には株式交換と同様の会計処理となります。
完全子会社となる会社が2社以上の場合(共同株式移転)を例にとると、会計処理はパーチェス法が適用され、取得企業となる会社の株式は、適正な帳簿価額(簿価)によって算定されます。一方、被取得企業に当たる完全子会社の株式は、取得の対価+取得に直接要した費用となります。ただし、株式移転においては完全親会社の株価は存在しないため、取得企業の株価を用いて交付した対価の金額を算定します。